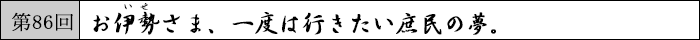文 江戸散策家/高橋達郎

『伊勢参宮 宮川の渡し』広重 (文政13年のお蔭参りの情景) 神宮徴古館所蔵
この人出はいったいどうしたことか。それに皆にこやかに笑っている。同じ着物を着込んで唄い踊っている一団もいる。楽しそうでお祭りのようでもあるが、これは伊勢神宮へのお参りの人たちだ。江戸時代、人々はこのような旅をするのが最大のレジャーだったのかもしれない。浮世絵のなかには「おかげまいり」や「御蔭参」と染め抜いた幟旗をかかげている人がいる。「お伊勢参り」のことを、江戸の後期には「お蔭参り」とも呼ぶようになった。お伊勢さまのおかげで日々の生活ができるという感謝の気持ちからからきた呼び方だろう。この場面は渡し船の順番待ちというところか。川に入って、参拝のために身を清めている男たちもいる。伊勢神宮は、この宮川を渡って約1里だ。
江戸時代、人は皆、伊勢を目指したといってもいいくらいである。「一生に一度はお伊勢さま」の言葉を裏付けるかのように、当時の史料には驚くほどの参宮者数が記録されている。
本居宣長(もとおりのりなが)が著した『玉勝間(たまかつま)』には、寛永2年(1625)閏4月9日より5月29日までの50日の間、合わせて362万人がお参りしたと記されており、享保3年(1718)の正月元旦より4月15日までは、合わせて42万7500人とある。国学者本居宣長は伊勢松坂の出身だ。
また、『御蔭耳目第一』によれば、文政12年(1829)の遷宮の年、3日間の神事があったとき、118万人の参詣人が群衆したという。
お蔭参りは、江戸時代を通して流行した社会現象である。それは不思議なことにほぼ60年周期で発生した。大きな山は、慶安3年(1650)、宝永2年(1705)、明和8年(1771)、文政13年(1830)が知られている。特に文政13年のお蔭参りは規模が大きく、数百万人といわれ、その頃の日本の人口を約3千万人とすれば、何と6人に1人位は参拝したことになる計算。
お伊勢参りにもう一つ特徴的な現象がある。それは「抜(ぬ)け参り」と呼ばれたもの。伊勢神宮に参詣するという意味では、「お伊勢参り」も「お蔭参り」も「抜け参り」も同じである。
「抜け参り」というのは、家の人に黙ってお伊勢参りに出かけてしまうことをいう。前述の宝永2年のお蔭参りのブームは、子どもの抜け参りが発端となった。心配した親がまた追いかけるように抜け参りすることも多かっただろうと思う。
しかし、信じられないようなことだが、当時の社会は抜け参りを容認したのである。お伊勢さまに詣でることは人間の善行とされる以上、誰も非難できないという風潮があった。例えば、江戸の店で働く奉公人が抜け参りをして帰ってきても、叱ったりしてはいけないのである。主人は咎めることなく、無事の帰参を目出たいと喜ぶくらいの器量が必要だったようだ。このことは『浮世の有様 ぬけ参善悪教訓鑑』(矢野太郎編1917年刊)に詳しい。
いつ頃からか、伊勢を目指す旅人は柄杓(ひしゃく)を携えるようになった。今も参拝の前に手水舎(てみずしゃ)で手を洗い口をすすぐときに使う、あの柄杓である。抜け参りをする人にとって柄杓は重要な意味をもつ。お伊勢参りの目印になり、道中あちこちで施行を受けられた。抜け参りの流行にはこんな背景もあったのだ。食べ物や金銭を柄杓に入れてもらえたり、ときには泊めてくれる家さえあった。そこにはみじめなイメージはあまり感じられない。施行する側も、参拝者を助けることは神徳を高められると考えたため、無理のない範囲で協力してくれたのだった。まさにお蔭参りである。
なぜこのように人々はお伊勢参りに駆り立てられたのだろうか。参拝が目的にしても、半分は物見遊山の旅を楽しみたかったのが正直なところだろう。江戸時代は社会が安定し、街道も整備されて、庶民にも少しばかり生活に余裕ができた時代である。旅へのあこがれは誰にもあったはずだ。大ヒットした滑稽本(こっけいぼん)、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』も後押しした。弥次郎兵衛(やじろべえ)と喜多八(きたはち)が楽しくお伊勢参りに行くという話だ。刊行されたのは、文政13年に流行したお蔭参りの少し前である。
伊勢神宮は、ただ「神宮(じんぐう)」というのが正式称号であるとパンフレットにはある。現在、神宮は内宮(ないくう)の皇大神宮(こうたいじんぐう)と、外宮(げくう)の豊受大神宮(とようけだいじんぐう)の二宮を中心に、十四の別宮(べつぐう)、百九の摂社・末社・所管社から成り立っている。内宮と外宮は約5キロメートル離れていて、外宮、内宮の順でお参りするのがよさそうだ。その後は、内宮前の「おかげ横町」で食事を楽しむのもいい。ここは江戸時代のお蔭参りの頃の様子を再現した町だという。
平成25年は式年遷宮(しきねんせんぐう)の年で、参拝者や観光客が多いと地元の人に聞いた。遷宮が一段落した11月に訪れた折りもたいへんな賑わいである。まだまだ別宮の遷宮が引き続き行われており当分混雑が続くだろう。遷宮が執り行われて初めて迎える新年、初詣は相当な人出を覚悟して出かけたほうがよさそうだ。



『縞揃女弁慶 竹屋直成』国芳 (伊勢暦を見る女性)
出典:国立国会図書館貴重書画データベース
御師は「おし」とも読むが、伊勢神宮の場合は「おんし」と読む。彼らは神社側のいわば営業マンや広告マンといったところで、手代(使用人)を幾人も連れて地方に出向き人々に伊勢参宮を勧誘した。御師の活躍があってこそ、お伊勢参りが全国に普及したといっていい。江戸時代に伊勢神宮の御師は全国津々浦々を行脚して信仰を遠隔地に伝え広めたのである。
御師は、ただ漫然と布教したわけではない。そこには工夫があった。「天照皇大神宮」や「豊受大神宮」の文字が摺られたお札(ふだ)を各戸に配り、初穂として金銭を受け取った。その返礼として伊勢土産を置いて行ったのである。その代表が現代のカレンダーに相当する「伊勢暦」だった。伊勢暦には、八十八夜や二百十日など農事に関する記載があるのが特徴で、農家には特に喜ばれ重宝された。江戸時代には、薩摩暦、京暦、三島暦、会津暦などそれぞれの地方に出回った「地方暦(ちほうれき、ちほうごよみ)」が存在したが、伊勢暦は発行部数もかなりの数にのぼり、多くの人が使った暦である。
想像するに、御師は訪問先で、伊勢の素晴らしさや天照大御神(あまてらすおおみかみ)の神話を語り、豊受大御神(とようけのおおみかみ)は「食」の神であること、つまりは「豊作を祈るにふさわしい神」であることを伝えたのだろう。そしてお伊勢参りを勧めたのではないか。また、実際に信者(施主)として伊勢を訪れたときは、半端ではない接待をした。その内容は多くの史料に残されている。
御師はもともと「御祈祷師」だったらしく、末法思想が出てくる平安時代には貴族の祈祷をしていたと思われる。江戸時代にも参宮者の要請で邸内の神楽殿(かくらでん)で神楽奉納を執り行っていることからも、祈祷師であり、神職のような立場だったことが分かる。
通常、御師は伊勢神宮近くに大きな邸宅をもち、神楽殿があり、旅館のようでもあり、そこに働く人も大勢いた。参拝者(多くは団体)の出迎えから、宿の提供、食事の提供、参拝への案内も伊勢観光も面倒をみるといった具合で、建て前としては全部無料である。御師は、参拝者を十分満足させたのである。料金は、神楽奉納や初穂、祝儀として相応分を受け取るしくみになっていた。
そのような話を聞けば、誰もが伊勢に行ってみたくなるのは自然の成り行きだった。しかし伊勢から遠い国の人たちは、そう気軽に行けるものではない。そこでできたのが「伊勢講(いせこう)」と呼ばれるグループである。同じ地区の仲間で、集落で、仕事の仲間同士でお金を積み立て、代表者数人(くじ引きなどで決める)に伊勢参りに行ってもらうというもので、お金の都合がつけば大勢揃って行くこともできた。伊勢講は全国各地に規模の大小こそあれ、相当数あったと思われ、それぞれ決まった御師が伊勢で迎えてくれたのだ。
団体で行く伊勢講は多額の費用を要したものの、知り合い同士の楽しい旅になったことだろう。お伊勢参りはこの伊勢講として参拝する人たちが多く、団体旅行の走りともいえそうだ。御師はまるで現地のツアーコンダクターのようである。
文章・画像の無断転載を禁じます。